AI時代の英語教育: 未来に向けて必要な挑戦とは?(後編)
- Jun 21, 2024
- 6 min read

▪️ まえがき
前編の記事では、AIの普及や機械翻訳の技術進化に伴い、言語スキルの市場価値が将来的に変化する可能性について述べました。今回の後編では、今後の外国語学習や教育において必要な挑戦について考察します。
▷ 目次
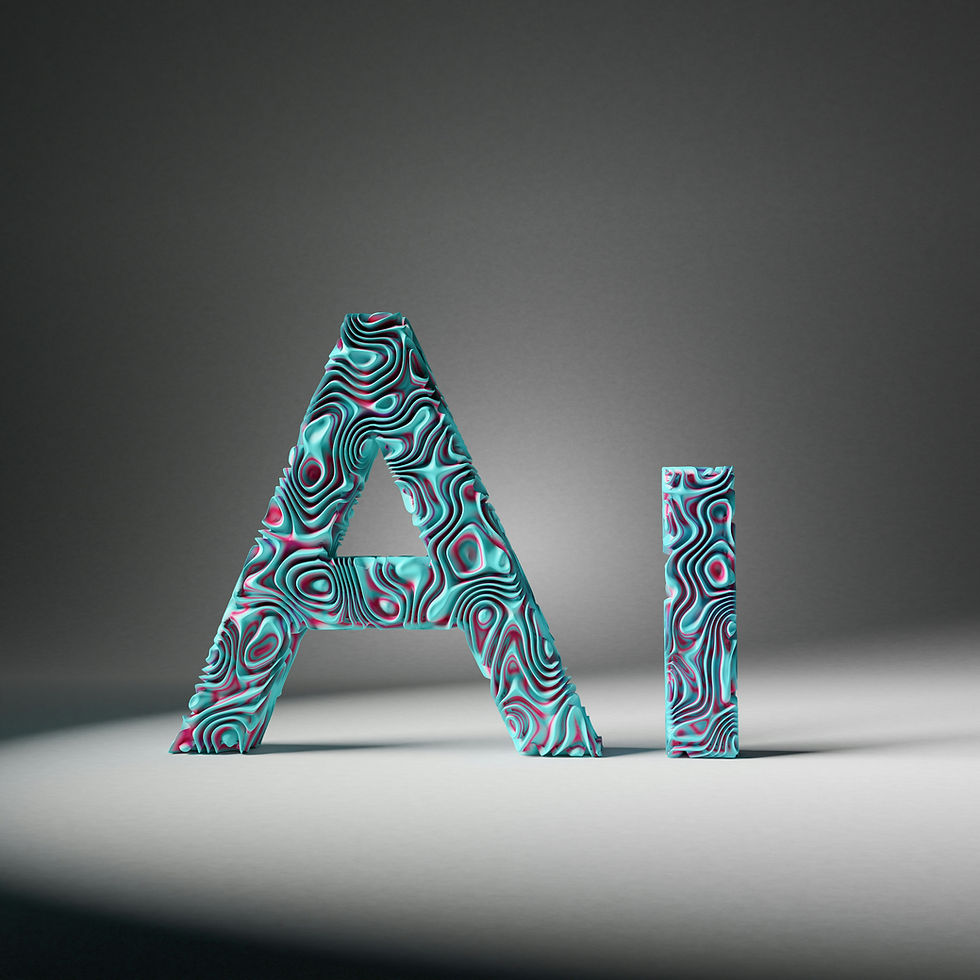
1. AI時代に言語を学ぶ必要はあるのか?
チャットGPTなどの生成AIの登場や、Google翻訳やDeepLなどの機械翻訳の精度向上は、英語の使用法や学習法に大きな影響を与えています。AIツールに仕事を頼めば、滑らかでミスのない文章を作成してくれますし、瞬時に翻訳もしてくれます。さらに、最近では同時通訳をしてくれるAI通訳機械も登場しています。これらのAIツールの普及は、語学学習において歴史的な変革をもたらしていると言えます。私たちは、外国語学習の意義や目的を見直す段階に来ていると感じます。
では、私たちは今後も外国語を学ぶ必要はあるのでしょうか?私の見解を結論から述べます。他言語間で人とのコミュニケーションが必要とされる限り、言語学習はなくならないと私は考えます。
海外生活で人との対話の場面を想像してください。ビジネスの場での交渉、学校の先生との面談、病院での診察など、多くの場面で英語による対話が必要です。そうした場において、あなたはAIを介したコミュニケーションだけで十分に満足できるでしょうか? 相手の人柄やニーズを理解し、信頼関係を築くためには、直接言葉を交わすことが重要です。もちろん、相手の言語が理解できない場合はAIや翻訳ツールを利用せざるをえませんが、強い信頼関係を築くためには、ダイレクトに言葉を交わして気持ちを通じ合わせることが不可欠です。ですので、人が人と心を通じ合わせようとする限り、言語学習はなくならないと思います。(また、人間はそのようであって欲しいと願います。)

2. 「言語スキル」と「非言語スキル」を分けて考える必要性
優れたAI技術が登場する中で、なぜ今後も外国語学習は必要とされると考えるのか。それには、理由があります。それは、AIが入り込めない領域があるからです。
私は、言語学習には、大きく分けて「言語スキル」と「非言語スキル」の2つの習得があると考えます。「言語スキル」に関しては、AIの正確さとスピードには人間は太刀打ちできなくなりつつあります。一方で、「非言語スキル」はAIが十分に能力を発揮できない部分、つまり、人間がコミュニケーションに価値をもたらし、意義を与えることができる「聖域」が残されていると私は考えます。
具体的に述べましょう。「言語スキル」というのは、従来、4技能と言われる、「読む・書く・話す・聞く」です。言語学習の核となる部分で、多くの場合、ある言語を運用できる状態になることを目標に指導が行われます。単語や文法の学習もこれに含まれます。
では、「非言語スキル」とは何でしょうか。それは、言語学習を「通して」身につくスキルです。「通して」というのがポイントです。直接的に学ぶ対象ではないのです。例えば、外国語を学ぶ過程の中で、自国の言語文化に対する新たな洞察が得られたり、異なる文化間での共通点や相違点を認識できるようになったり、国際社会でのコミュニケーションにおいてより柔軟なアプローチを取ることができるようになったりするスキルが例に挙げられます。

3. 「非言語スキル」は、言語の壁を乗り越える真の力
少し話が抽象的だったので、ここに私が考える「非言語スキル」の具体例を挙げます。私は時折、通訳の仕事をしておりますが、日本人の方のこのような発言を通訳する場面によく出くわします。
例1:「つまらないものですが、どうぞお受け取りください。」(英訳:It’s nothing special but please take it.)
例2:「私のプレゼンはそんなに面白くありませんが、聴いてください。」(英訳:My presentation may not be very interesting, but please give it a listen.)
これらの発言を、そのまま上記の英訳で伝えたとしたら、相手(=英語話者)は不思議な顔をするでしょう。例1であれば、「つまらないものとわかっているのに、なぜ差し出すのか。」そして、例2であれば、「どうしてもっと面白いプレゼンに仕上げてこなかったのか。」と考えると思います。
こうした日本人の何気ない発言の背景には、「謙遜」という日本独自の概念が含まれています。しかし、他の文化においても謙遜の概念があるとは限りません。「非言語スキル」には、相手の文化に対する理解も含まれます。相手の文化的背景を理解していれば、謙遜から生じる上記のような発言は、相手に必ずしも良い印象をもたらすとは限らない、と考えることができます。そのような考えをもとにすると、それぞれの例は以下のように変えられます。
改善例1:「気に入っていただけると嬉しいです。どうぞ。」(英訳:I hope you like it. Please take it.)
改善例2:「多くの人に興味を持っていただけるようなプレゼンにしました。聴いてください。」(英訳:I've tried to make it an interesting presentation for many of you, so please give it a listen.)
こうした例が示すような、言語の背景にある文化的要素や、言葉の真の意味を理解して相手に伝えるというスキルは、まだAIや機械翻訳が入り込めない領域です。英語で “Cultural Sensitivity” 「文化的配慮」とも言いますが、こうした非言語的スキルは、言語の壁を乗り越える真の力だと思います。異なる言語を介在するだけでなく異文化間の相互理解を促進することのできる人材が、今後、より重要視されると思います。

4. 言語学習の新たな方向性
これまで述べたように、「非言語的スキル」には、外国語を学ぶことで他の言語や文化に対する理解が高まる、母国語に対する理解が促進される、国際社会の相互関連性を認識できる、といった要素が含まれます。この部分について、これまでの言語教育ではあまり明確化されず、曖昧にされてきた印象を受けます。しかし、これからのAI時代、言語教育の意義や目的が求められるようになると、この「非言語スキル」は、より明確にされ、強調される必要があると考えます。なぜなら、これらは、異なる文化間の意見や背景の違いを理解し、円滑な対話を可能にする力を持っているからです。言語学習は、単に単語や文法を覚えるだけでなく、異なる文化やコミュニケーションの背景に触れ、その言語を通じて他者との理解を深めることも含まれます。これはAIが代替できない人間の特性であり、言語学習を通じて養われる重要な能力であると考えます。今後の外国語学習では言語スキルだけでなく、(あるいはそれ以上に)非言語スキルの習得が強調される必要があると思います。

まとめ
哲学者であるマルティン・ブーバーは、著書「私と汝」(I and Thou)の中で、人間の本質的な存在を他者との関係に見出し、対話を通じて人間が成長し、自己を理解すると主張しました。これが未来においても通用するのであれば、人間同士のコミュニケーションはなくなることはなく、それによって、人間が人間として存在する意義をもたらします。
よって、人と人との間にコミュニケーションの重要性がある限り、そして、世界に多言語が存在し続ける限り、外国語学習はなくなることはないと思います。今後の外国語学習は、AIが学習をサポートするやり方が主流になっていくと思いますが、上記に述べた「非言語スキル」には人間の力(あるいは、人間らしさ)が求められます。そのような状況である限り、外国語での直接的なコミュニケーションの価値は失われることはなく、外国語学習も価値を持ち続けると考えられます。
EBLS -Enrichment Bilingual Language Services 代表、教育コンサルタント 二階堂 香瑠 Email: info@ebls.ca Web: https://www.ebls.ca/ | |
\ ご案内 /
当校EBLSでは、オンラインによる英語レッスン、英語試験対策レッスン(TOEIC、IELTS、CELPIPなど)を行っております。
お問い合わせのページからお気軽にお問い合せください。
























Comments